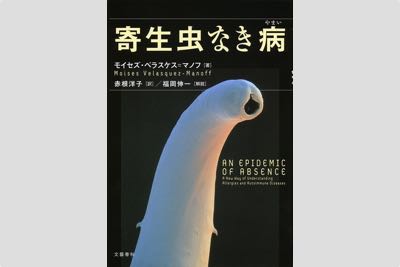この本は、臨床医学の現状に即しつつ、 基礎医学的知見に歴史や環境変化をからめた包括的な理論として、面白いです。この本の原題は、 「不在の病」 「不在という流行病、アレルギーと自己免疫疾患についての新しい理解」です。「不在の病」って、奇妙な表現です。いったい何でしょうか。
この本では、 現代になぜこれほどアレルギー疾患・自己免疫疾患、たとえば花粉症、食物アレルギー、ぜんそく、リウマチなどが増えているのか、という問題に対して、一つの答えを出しています。
(注:現時点ではあくまでまだ仮説です。アレルギーにお悩みの方は鵜呑みにして安易に真似をしないでください。)
この本の著者自身が重いアレルギー・自己免疫疾患を患っていて、それを治すためにあえてメキシコまで行き、 「アメリカ鉤虫」という寄生虫の卵を飲んで、 寄生虫を自身の体に住まわせ、自分の自己免疫疾患を治した人だそうです。 日本にも藤田紘一郎先生という、 「カイチュウ博士」があえて自ら回虫に感染しています。彼らはなぜそんな汚らしく危険なことをするのでしょうか? その根拠がこの本には詳しく書かれています。
まず、イタリアのサルディーニャ島の例が挙げられています。この島では、この50年で急激に多発性硬化症という自己免疫疾患が急増しました。 難病である多発性硬化症は、一般にはまれな病気ですが、この島では異常に発症者が多いのです。その原因につき、ある研究者が、1960年代にこの島でDDT散布によるマラリアの撲滅をしたことが原因だと考えました。その理由は以下の通りです。
サルディーニャ島の人は、長い歴史の中で、マラリア原虫と共存する体質を獲得しました。 赤血球の中に入り込み、 時には脳の中に入り込んで致命的な症状を引き起こす、恐ろしいマラリア原虫。その原虫が人間の体の中に入ってきたときに、 原虫を生かさず殺さず、かといって自分も原虫に殺されずに、 原虫と共存していくための生存戦略としての複雑な免疫システムを、 数千年にわたるマラリアとの戦いの歴史の中で、サルディーニャ島の人たちは獲得してきました。その遺伝子的・生理学的な変化の詳細がわかってきているのです。 (詳細は原著を参照ください)
50年前のDDT散布によって、この島でマラリア原虫が撲滅された時、 島の人にとっては「戦う相手」が突然「不在」になったのです。その時、相手を失った免疫システムは、 自己の身体を攻撃するようになってしまいました。それにより多発性硬化症などの自己免疫疾患が島の人々の中に急増しました。それは、まさに敵が「不在」になることによって失調をきたす、 「不在の病」だというのです。
この病理理論が妥当ならば、マラリアほど病原性が強くない病原体を人間の体の中に共存させれば、多発性硬化症などの難病の発症を防ぐことができる、というのです。お気づきになった方も多いと思いますが、この理論は、進化論的な考え方に基づいています。「原因ウイルス」 「原因遺伝子」「原因脳内物質」を探すという「ハードサイエンス」とは異なり、 生態系や、生物の複雑なシステムを念頭に置きながら、 生命進化の歴史をも射程に入れた、 包括的な科学(ソフトサイエンス)の病理理論なのです。この本には、 「生物学においては、進化を考慮に入れなければ何も理解できない。」という生物学者ドブジャンスキーの言葉が引用されていますが、その見解には臨床医の私もまったく同意します。
それでは、私たちが相手にしている精神疾患、例えばうつ病について、 生体防御システムが環境変化により失調を来した、 「不在の病」と考えられるでしょうか。著者はそう考えています。ガンにもうつ病にも「炎症反応」「免疫」が関係するとします。 例えば、このような感じです。
「上司に怒鳴りつけられるといったストレスフルな出来事は、 明らかに憂鬱な気分を引き起こす要因となる。 急性のストレスは激しい炎症性の免疫活動を誘発する。・・・現代社会においては、 炎症は恒久的なフィードバックサイクルに陥りがちになっている。・・・社会的なサルである我々人類にとって、孤立は不健康だ。しかし、『旧友』(水谷注:腸内細菌や寄生虫など微生物のこと)との接触を失ったために我々の免疫系が炎症に傾きがちになったことを無視するわけにはいかない、・・・子ども時代に微生物から正しい刺激を受けていれば、 上司の叱責にももっとうまく対処できるかもしれない。 微生物や寄生虫から教わった免疫寛容は、 感情的な寛容さに直接つながっているのだ」
確かに、面白い考えです。
臨床的には、うつ病患者さんが胃炎やアトピー、神経炎などを患い、 実際に体内に炎症性の病気を起こしていることは多々あり、 消炎鎮痛剤を服用している人も多々います。
また、うつ病を病む人の中に、 上司からのパワハラや過剰労働など大変なストレスを受けながらも、 不満や怒りの感情を全く表さず、そのような炎症性疾患の合併症を起こしていた人が、ちょっとした愚痴や苛立ちの気持ちを口にできた時、 炎症症状とともにうつ病症状が改善することがあります。 自分の仕事ぶりや現在の自分の社会的立場が納得できず、 自分の現状に不満で自分に怒っているような人が現状の自分を受け入れられると症状が良くなることもあります。
それはまさに、体の中にある「炎」のようなものを「吐き出す」ことで病状が良くなったようなイメージです。
そのように、私がうつ病の患者さんを診療していると時々、 彼らの体の中に何か、戦いのような怒りのような、 何かがうごめく、「炎症」のイメージを感じることがあります。 彼らが自分にも他人にも厳しすぎて、 「寛容」さを失って窮屈な生き方になってしまっている、そんなイメージを受けることもあります。
著者ベラスケス=マノフの、 「免疫寛容は感情的な寛容さにつながっている」と表現は、あくまでも比喩としてですが、 臨床精神科医の実感に近いものがあります。
ただ、ここまでがこの本のうつ病の病理理論の限界で、 「こうした事実は、免疫機能に働きかけてうつ病を治療するという新しいアプローチの可能性を示唆している。・・・腸内細菌叢の乱れを直せば、うつ病も治るかもしれない。 糞便移植(おそらくは明るい性格のドナーから採取した腸内細菌入りの) が臨床的うつ病の標準的治療法となる日がいつか来るかもしれない。」という、微生物と免疫についての話の一本槍で終わるのです。 (「明るい性格」を作る細菌! そんなのあるのでしょうか?)
それでも、このような観点は、うつ病治療につき、 薬物療法や電気けいれん療法といった、 脳を操作することばかり考えているような生物学的研究に対して、 一つの対抗する考え方を提示しており、興味深いと思います。